連日、大雪のニュースが続いています。
東京都心では雪こそ積もりませんが、寒い日が続きます。
この時期になると数年おきに、カエル観察に行く場所があります。
都心からみると、奥多摩まで行かない手前なので「てま多摩」とでも言いましょうか。
今回の舞台はそんな多摩川水系のとある支流になります。
谷の中の気温は昼を回っても5℃前後、天気は良いのですがこの時期の低い太陽光はほとんど注ぎません。
別会社の知人と、沢筋に足を進める休日の午後です。
目的地は流れの合流部付近にある、いわゆる「たまり」。
その場所は以前と大きく変わらずありました。
長さ5m幅3mくらいのプールで、水深は約40cm、水の流れが緩やかになり、大きめの岩がいくつか沈んでいます。
そのような環境は渓流内にたくさんあるので、おそらく他の場所でもよいのでしょうけれど、なにぶんアクセスがよいので、ついつい楽をしてしまいます。
到着するとすぐに川底に沈む「お宝」を発見しました。
数匹の「ナガレタゴガエル」が我々の気配に気づいて、岩陰や落ち葉の中へモゴモゴと隠れていきます。
このカエルは渓流に生息し、2~4月に産卵する種で、生きものとしては比較的最近になってから、名前がつけられたカエルです。
この渓流でも、どうやら今年も無事に繁殖期が始まったようです。
卵でお腹がパンパンに膨らんだメスに、ぶよぶよのオスが必死でしがみついています。
そのたまりでは、産み出された卵はまだ確認できなかったので、少しだけ時期が早かったかもしれません(2月11日)。
昨秋、個人の趣味で購入した一眼用のハウジングにて、冷水に手を突っ込んで水中撮影を試みました。
かじかんで思うように動かない指先に季節を感じました。

ナガレタゴガエルのペア
カメラ機種 : SONY ILCE-6000
レンズ:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
露出制御モード : プログラムAE
レンズの焦点距離 : 30.00(mm)
シャッター速度 : 1/60秒
レンズF値 : F5.0
露光補正量 : EV0.0
フラッシュ : 強制発光・リターン不検出
ISO感度 : 2500
トリミング:あり
両生類・爬虫類、哺乳類担当 釣谷洋輔

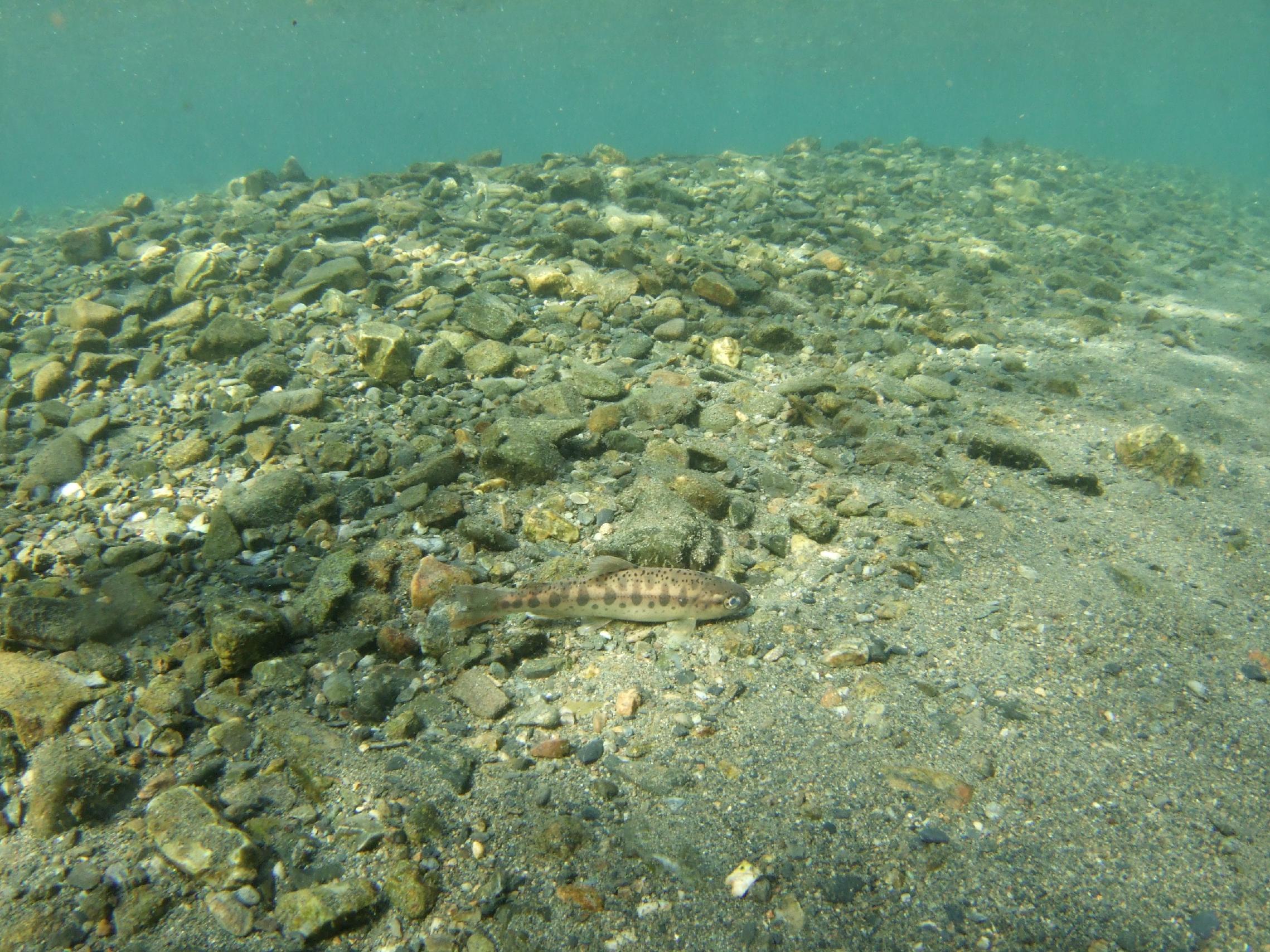



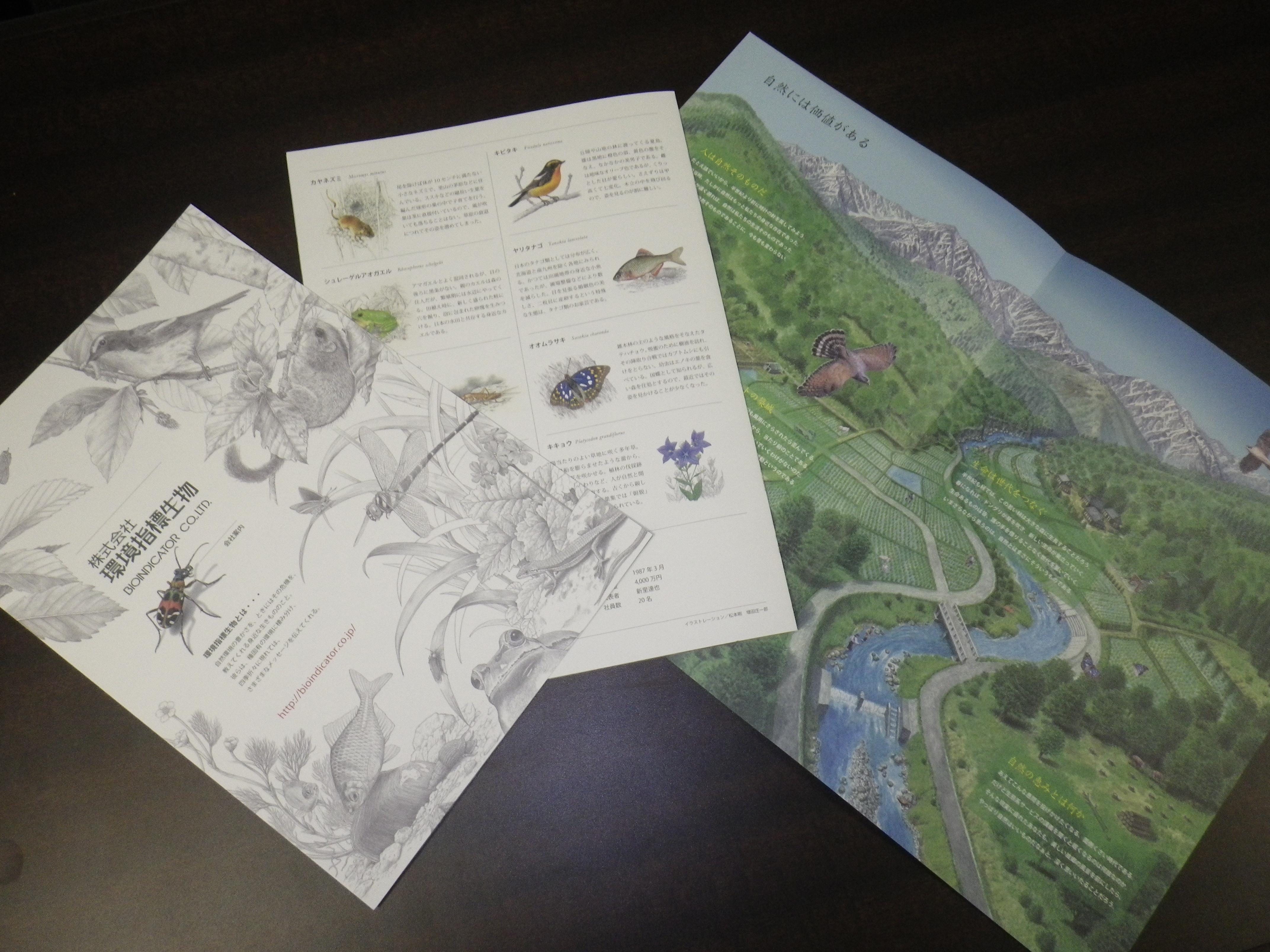

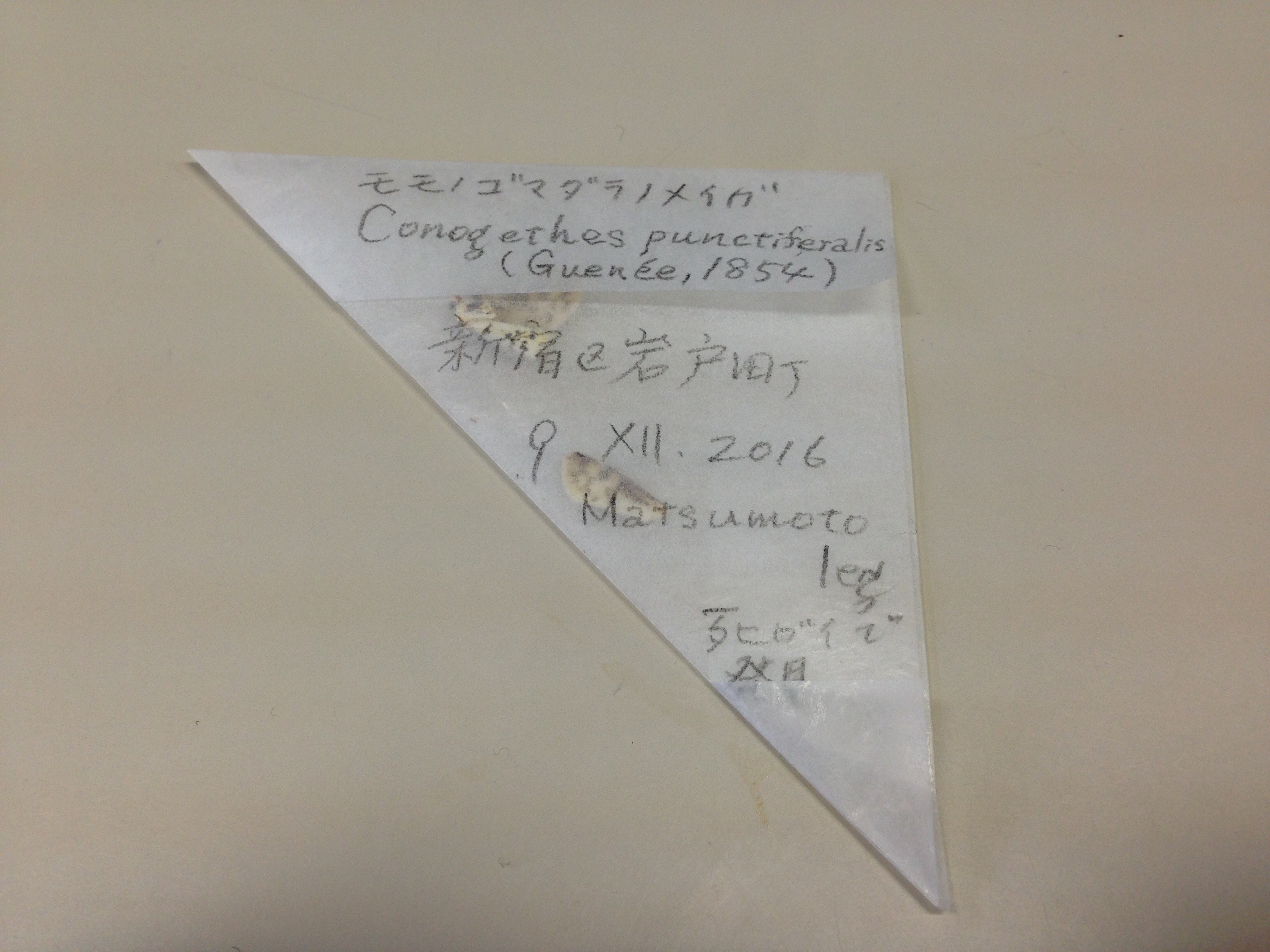





最近のコメント