8月15日、78回目の終戦記念日を迎えました。新聞などで見る、戦災体験を語る人々の年齢も気がつけばかなり高齢になり、戦争の悲劇を肌がひりひりするような実感を伴って伝えていくことが今後ますます難しくなっていくことを感じます。一方で、ロシアのウクライナ侵攻以来、世界の安全保障の潮流が大きく変わり、長く平和主義を掲げてきた我が国もその例外でないことが気がかりです。
【都内の戦災構造物】
あまり知られていませんが、私の地元、東大和市には「旧日立航空機株式会社変電所」という戦災構造物があります(※1)。

東京の空襲というと都心部のイメージでしたが、この辺りは軍需工場があったため、先の大戦末期には空襲があり、従業員や動員された学生、周辺住民など多くが犠牲になり、壊滅的な被害を受けました。この変電所も、窓や扉は吹き飛び、外壁だけでなく屋内まで、機銃掃射や爆発物の破片により穴だらけになりました。
それが今日まで保存され、現在周辺は公園として整備されています。無数の弾痕を生々しく残した機銃掃射のあったこの空間に、生身の人間も多数いたことを思うと鳥肌がたつようです。いっぽうで、四季折々の花が咲き、家族連れで賑わう公園の風景は平和そのものです。この強烈なコントラストは異様でもありますが、戦争もすれば平和も愛する、私たち人類の二面性の映し鏡のようにも感じられ、悲しくも愛しいような、何とも言えない気持ちになります。
【戦争は人類の宿命か】
生きもの屋として戦争を考えるとき、進化生態学的に考えるともはやこれは、人類の宿命では、という考えに捕らわれることがあります。簡単に言うと「戦争が好きで得意な種族」と「平和を愛する種族」が鉢合わせて競合したとき、どちらがより多く子孫を残せるか?と考えると、おのずと前者に軍配があがり、後者は絶滅しそうです。結局は、現代に生を受けた私たちも皆、血塗られた種族の子孫。でも、本当にそうなのでしょうか。
【戦争のない20万年】
人類学を紐解いてみるとしかし、狩猟採集生活をしていた20万年もの間、「戦争」と呼べるようなものはほとんどなかったというのが定説のようです(※2)。考えてみれば狩猟採集生活では食糧も人口も密度が低いので、群れ同士が鉢合わせる機会も少なかったでしょうし、「戦争」を組織的に行うほど群れの規模が大きくなかったということ、誰もが定住しないその日暮らしでは襲撃のリスクを犯してまで奪うほどの物もなかったなど、その理由はいろいろな面から考えて合理的です。要するに戦争をするほどの余裕がなかったというのが実際のところかもしれません。
【農耕文化と戦争の因縁】
それが約1万年前、農耕が始まると劇的に状況が変わりました。食糧には土地に資源や労働を投資した対価としての意義が生まれ、土地や収穫物に対してそれまでなかった「所有」の概念が生まれました。富の集積と共同体の肥大(群れ→村→国家)が起き、階級が生まれ、身分格差が生じました。共同体が肥大すれば更なる土地が必要になり、周囲の別の所有者から奪うほかなくなりますし、富や権力に魅了された者が覇権を求めて戦争を繰り返したのは理解できます。
とはいえ、20万年以上の歴史を持つ人類が戦争を始めたのが直近の1万年というのは、少し意外でもありました。個人的には、もっと本能的な、根源的な衝動のようなものが戦争に関わっているような印象を持っていたのです。
【非互酬性と利他行動】
ところで、共同体のなかに目を向けると、類人猿と分かれた祖先の頃から、「非互酬的」な関係、つまり見返りを期待せずに何かを与えたり助け合ったりという「利他行動」が成立する関係が発達したと言われています(※3)。多くの動物でも、親子や血縁者においてはこうした関係は一般的ですが、それ以外を対象とした非互酬性はあまりみられません。私たちの祖先は家族が複数集まった共同体(群れ)単位で助け合って暮らしてきました。共同体の中にも血縁者がある程度いれば、こうした無償の利他行動は適応的になる(生存や繁殖の成功確率を増大させる)可能性があるようです。この特性は狩猟採集生活の頃には、「仲間のために危険な狩りに赴く勇気」といった形でも発揮されていたかもしれません。
このような、言ってみれば愛情深い性質は、農耕文化でも維持されました。しかし「共同体のために戦地に赴く」というように、共同体間では残念ながら、平和よりは戦争に向けて発揮されてきたのかもしれません。
【戦争の利害と対立軸】
さて、戦争で得をするのは多くの場合、支配者階級や、今日では軍需産業など一部のセクターの資本家に限られていて、状況をコントロールするのもそうした層です。一方で、戦争のコストを払うのは、いつの日も圧倒的多数を占める民衆です。よく言われるように、実際に死線をかいくぐるような戦地に赴くのも、住居や耕作地を追われ、大切な労働力を奪われ、略奪に遭い、家族を失うのも、多くは為政者や資本家ではなく、民衆です(※4)。人類が助け合って生きるために培ってきた普遍的な性質である非互酬性、利他性が、一握りの人たちの利益のために、「国家のため」「亡き同胞のため」といった巧みなプロパガンダなどを通じて利用されてきたとしたら、悲しいことです。
そうしてみると、「ウクライナに支援を」「ロシアに制裁を」というように、戦争が「国家対国家」の文脈で語られることに慣れきっている私たちですが、「権力対民衆」という別の、隠された対立軸が意識されてきます。
【平和主義と民主主義】
このような利害や、人類が戦争をするようになった経緯を考えてみると、権力は戦争に向かっていくもの、というのは残念ながら普遍的な傾向に思われてきます。では、平和のために私たちはどうすればよいのでしょうか。
意外なことに、その処方箋は戦後すぐに示されていました。日本国憲法の前文には「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、(中略)政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」とあります(※5)。戦争を起こさないためにも主権が国民にあることが大切なことがわかります。また、第三章第十二条には「憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」とあり、自由と権利、その先の平和のための、国民自体の努力を求めています。
要は私たちのひとりひとりの政治参加なくして、平和は守れないということは、70年以上前から分かっていたのです。省みて自分はその努力を惜しまなかったか。傷だらけの変電所に問われているような気がした、78年目の終戦記念日でした。
(代表 高木圭子)
※1 戦災建造物 東大和市指定文化財 旧日立航空機株式会社変電所(東大和市)
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/bunkasports/museum/1006099/1006102.html
※2 ヒトはなぜ争うのか 進化と遺伝子から考える(若原正己、新日本出版社)
https://www.shinnihon-net.co.jp/general/product/9784406059626
※3 NHKブックス No.1099 暴力はどこからきたか 人間性の起源を探る(山際寿一、NHK出版)
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000910992007.html
※4 平和主義とは何か 政治哲学で考える戦争と平和(松元雅和、中央公論新社)
https://www.chuko.co.jp/shinsho/2013/03/102207.html
※5 日本国憲法(衆議院)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm










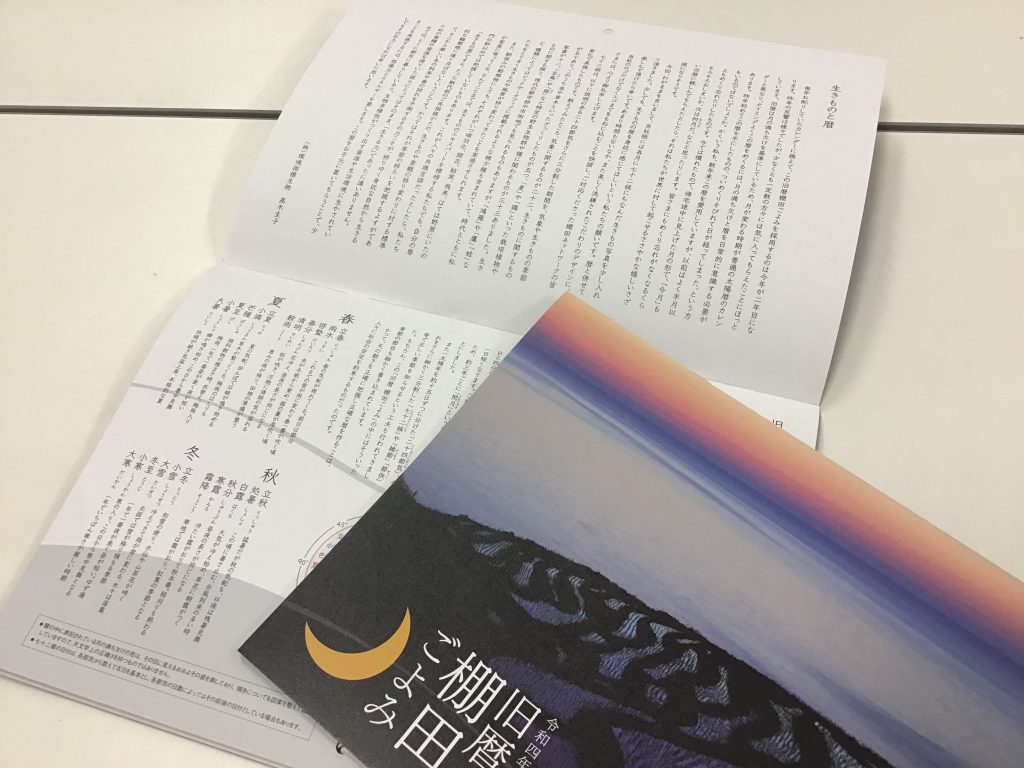
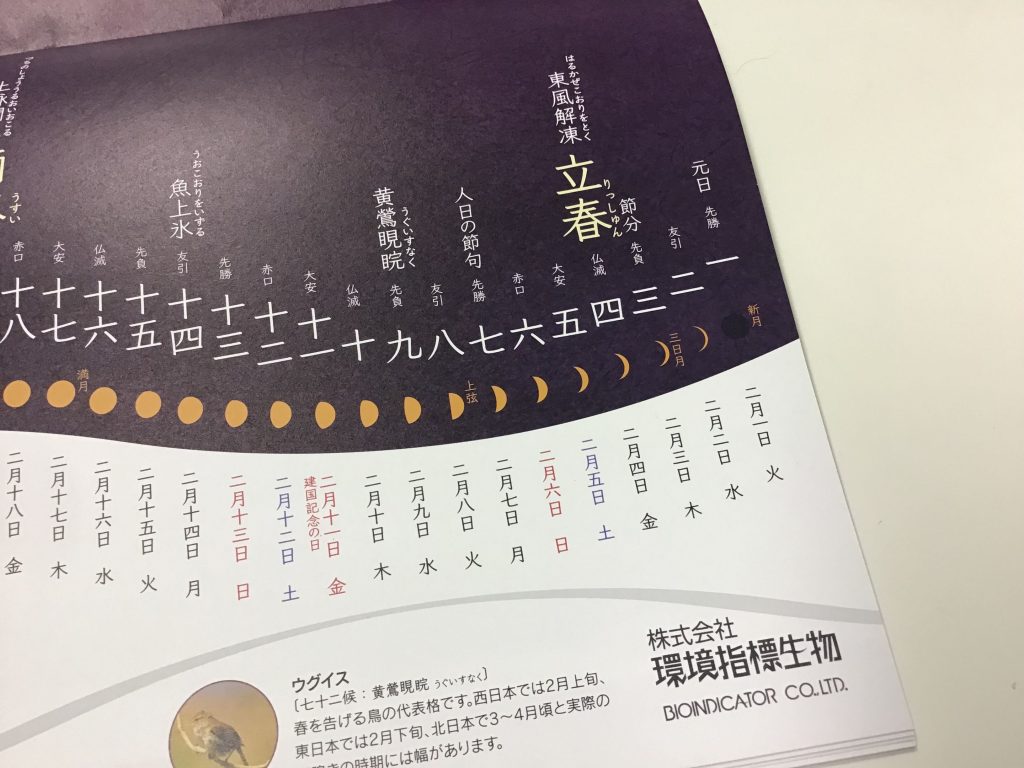
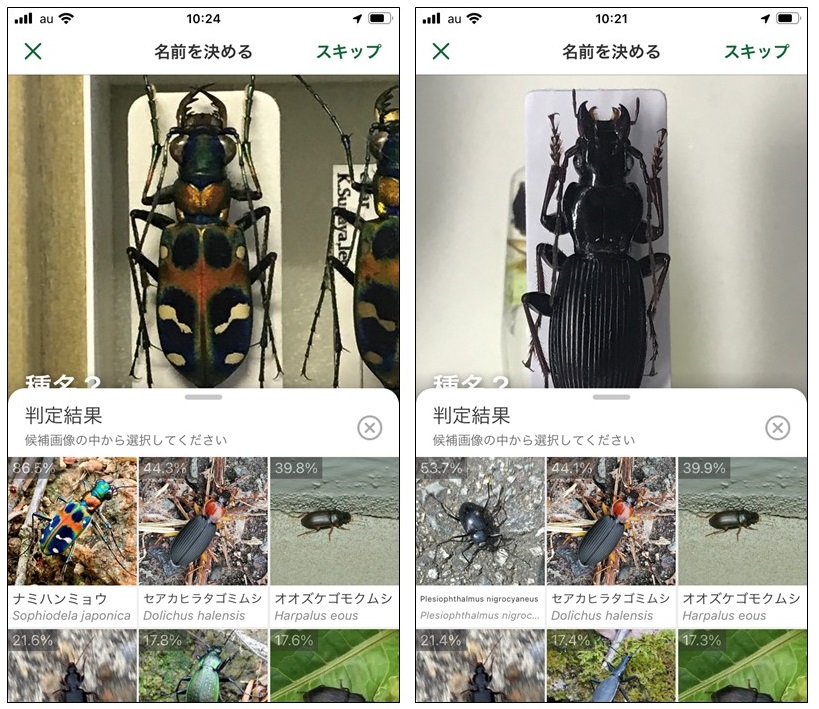
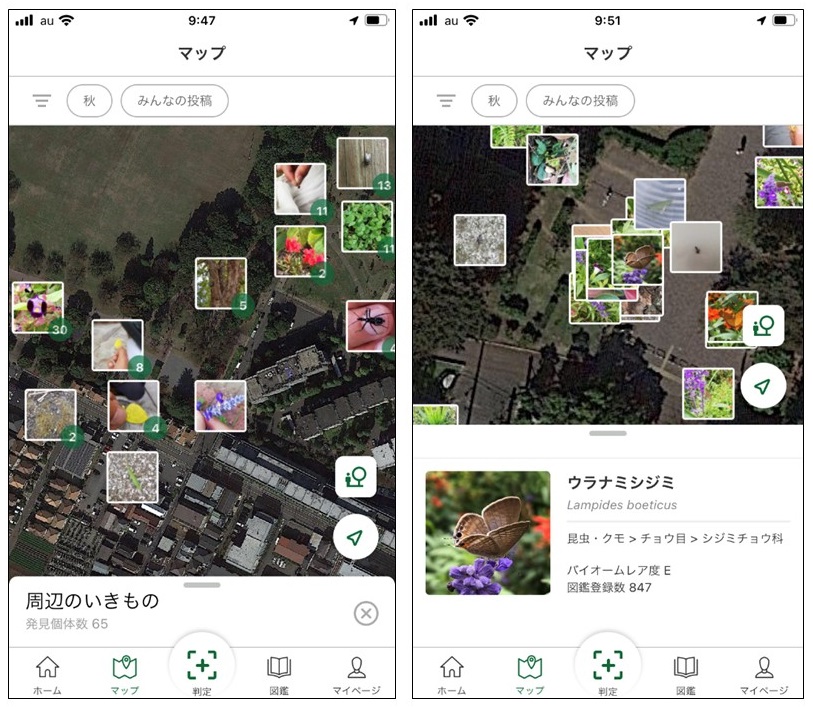


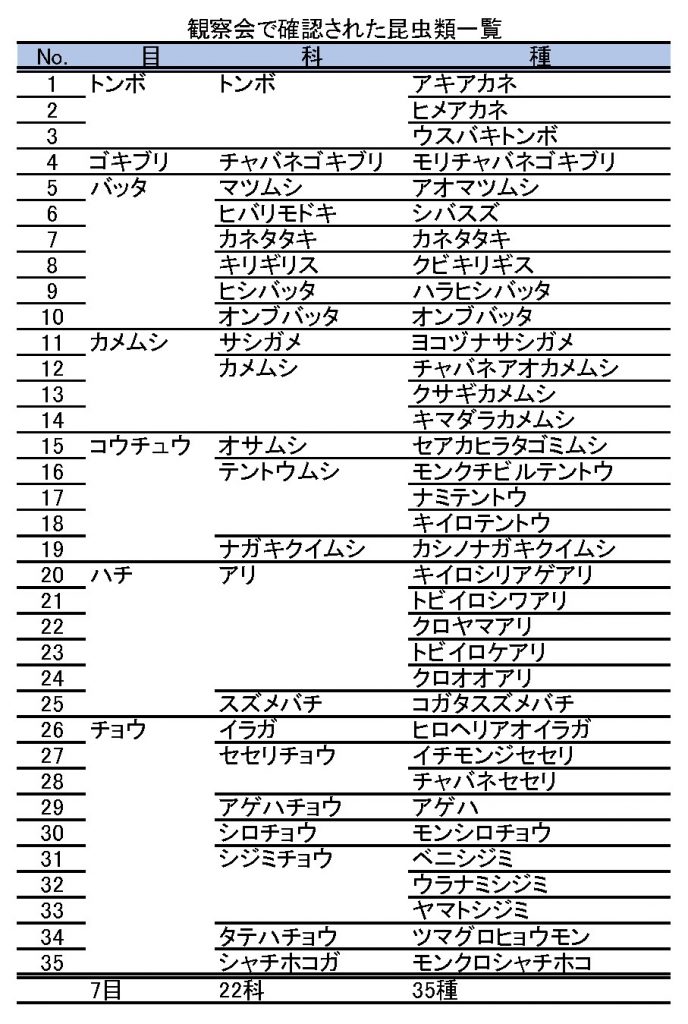
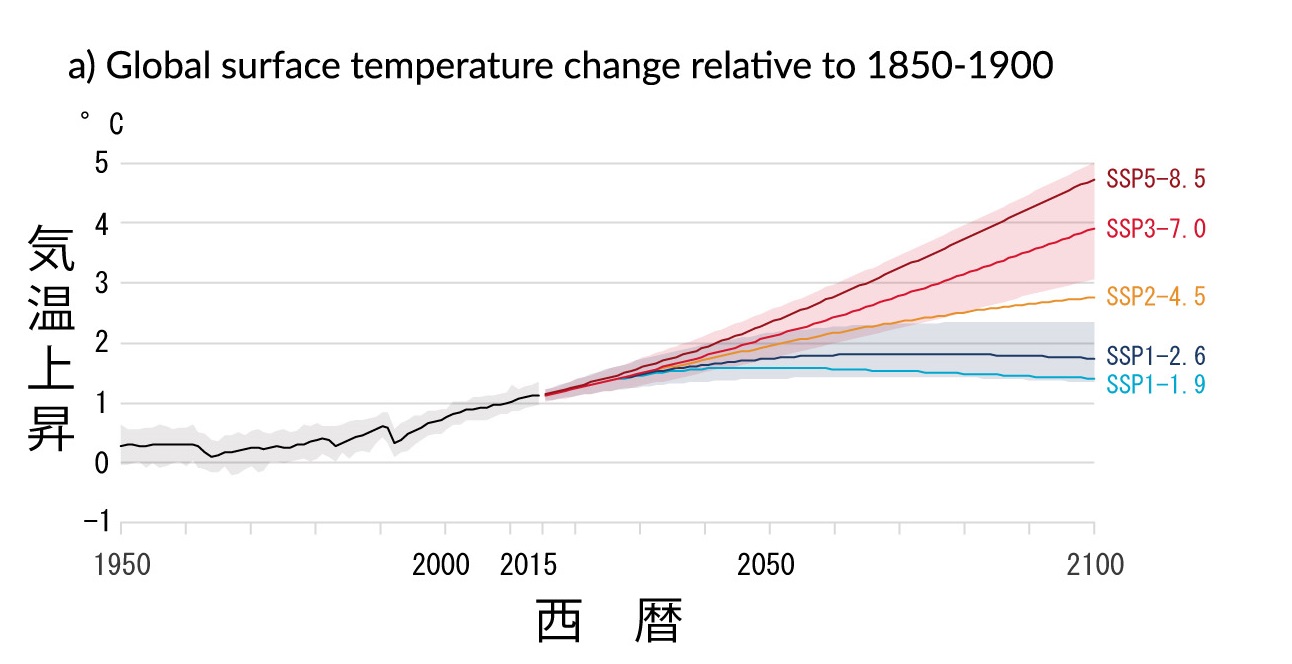
最近のコメント