10月も半ばを過ぎた頃から急に涼しくなってきました。
もう朝夕は半袖では肌寒いのですが、日中は汗ばむ陽気の日もあり寒暖の差が激しい頃です。衣替えしようか、どうしようか…。
そうこうしているうちに、10月23日からは「霜降(そうこう)」という露が霜へと変わる節気に入ります。
関東地方では9月30日に栃木県奥日光で初霜・初氷の便りが届いています。
平野部でも間もなく初霜がみられるでしょう。
今回は、とある東北地方の河川に調査に行ったときのお話。
昼食後、休憩をかねて河川敷の土手でひと休みしていると、なにやら川の水面がざわざわしています。数分おきに大きな魚が背びれを出して、浅瀬を登っていきます。観察のためこっそり近づいてみます。
60~70cmのサケが数匹ずつ川の深みに群れていました。この季節ならではの光景です。
ご存じのとおり、サケは川で産まれ、海で育ち、また産卵のために川へ帰ってくる遡河回遊性(そかかいゆうせい)のライフサイクルの魚です。
河口から遡上してきたサケは上流の産卵場所を目指して川を遡ります。
この母川回帰を英語では「サーモン・ラン」といいます。
産卵場所にたどり着くと、メスは川底の砂利を掘って産卵床を作り、約3,000個の卵を産みます。
産卵後、メスは自分の体で卵をおおって、卵を狙う外敵から守りますが、体力消耗のため、産卵後1~2週間でその生涯を終えます。
弱った個体や卵は、クマやキツネのほか鳥などの食糧となり、これから厳しい冬を迎える山あいの動物たちに、秋の恵みとして提供されます。
ひと昔前は防災や水利の関係で河川の構造が変えられ、魚の遡上が難しい河川も多かったのですが、最近は魚道を設けるなど、遡上する魚に配慮した構造をもつ河川が増えてきました。
多くの有機物は山から海へ流れていくものですが、「サーモン・ラン」のように海から山へ恵みを循環させるサイクルが、豊かな自然を維持する秘密なのだと、写真を撮りながら考えました。

遡上するサケ
カメラ機種 : OLYMPUS TG-4
露出制御モード : プログラムAE
レンズの焦点距離 : 46.00(mm)
シャッター速度 : 1/50秒
レンズF値 : F3.1
露光補正量 : EV0.0
フラッシュ : オフ(自動)
ISO感度 : 250
トリミング:あり
両生類・爬虫類、哺乳類担当 釣谷洋輔






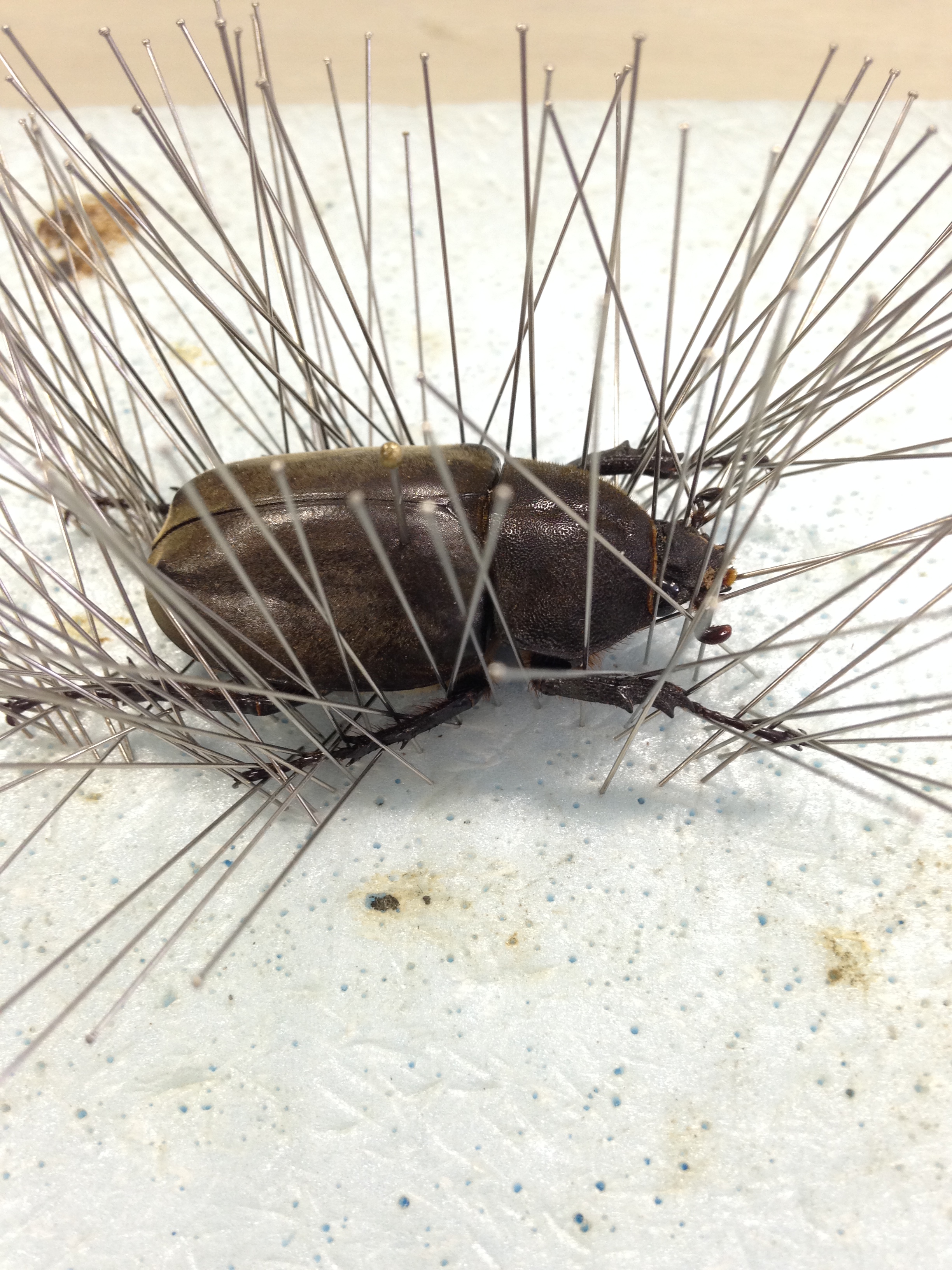



最近のコメント